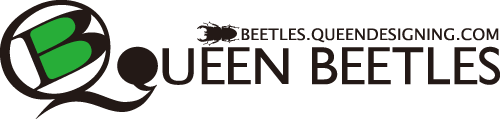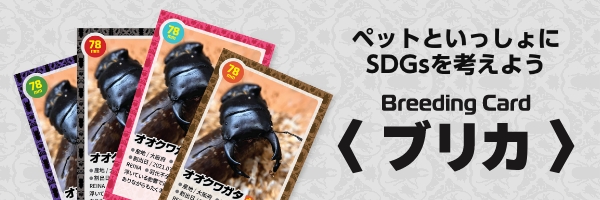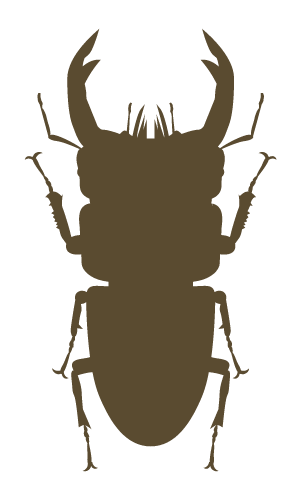標本作りで分かること
2021/07/28 [Wed] 標本カービィ、メタナイト、クラが死に、カブトもテンビンに続いて羽パカのキロギーがとうとう死んでしまいました。
キロギーは羽パカの割に元気で、ここ最近明らかに弱ってきていて、エサ交換をしても反応が薄い(とは言え相変わらずよく食う)子達が多い中、いつも大袈裟に反応してバタバタして、あっという間にエサに飛びついて食い尽くしていました。
自然界だったら、空も飛べずすぐに外敵に見付かって食べられるだろうと思いますが、キロギーの羽化不全はほぼ間違いなく羽化途中か何かの時にボトルを動かしてしまったことが原因だと思われるので、恐らく自然下ではあまり起こりにくいことでしょう。
反省の意味でもキロギーも標本にしようか、と言っていたのですが、いざ下準備してみると予想以上に損傷が激しく、よくこんな状態で生きていたな、と感心しました。
標本作りの手順
- 水洗いする
- エタノールに数日漬ける
- 再度水洗いしてからお湯に漬けて柔らかくする
- 形を整えて発泡スチロールなどの台にピンを刺して固定する
- しばらく乾かす
- 固定・補強のために適宜ニスを塗る
- 乾燥剤・防虫剤を容器に一緒に入れて保管する
どんな標本を作るにせよ、まずは洗って汚れを落とす必要があります。
土だけでなくダニもたくさん付いていたりするので、私は軽く水で流してから、水を入れた容器に少しの間漬けておき、筆で脚の間などを細かく洗うようにしています。
その後エタノールに漬けて、蒸発防止のためにサランラップを容器にピッタリと貼り、数日置きます。
再度取り出して水洗いしてからお湯に漬けて柔らかくし、形を整えて脚の周りにピンを刺して固定し、数日乾かします。
写真にもありますが、私は発泡スチロールの上に食器用スポンジを乗せたものを台にしています。
というのも、写真のようなネットの付いた食器用スポンジを使うと附節がうまい具合に引っかかって固定しやすいのです。
ちなみに私は仕上げに虫ピンは刺しません。
気軽に触れる子供のおもちゃにしたいからです。
虫ピンを刺さないで放置していると、乾燥のせいで数ヶ月経つと上翅が少し開き、附節が取れます。
今年はその対策のために接着剤とニスを使って補強するつもりですが、どうなるでしょうか。
標本作りで分かる死因
上に書いたのですが、羽パカのキロギーは損傷が激しく、最初の水洗いの時点で首がグラグラで取れてしまいそうな状態でした。
更に水やエタノールに漬けると、茶色い体液が出てきて悪臭がしました。
1日エタノールに漬けていたら体液はほぼ出きってだいぶマシにはなったものの、相変わらず悪臭がしていました。
ツノも今にも取れてしまいそうで、やはりこれは標本にするのは難しそうです。
同様に洗って水やエタノールに漬けても、全く体液なども出ず異臭もしない方が多いのですが、メタナイトは少しだけ体液が出ていました。
首もややグラグラしていましたが、メタナイトの場合はエタノールに漬けて数日置いていたら硬くなり、普通に標本が作れる状態になりました。
詳しいことは分かりませんが、体液が出る場合は外傷があり、それが死の原因になったとも考えられると思います。
附節も残っていてきれいな状態で死んだ場合は、何かの病気や、メスだと産卵の影響も考えられるのではないでしょうか。
昨年産卵後に急死したピグリンや、カービィはこのケースでしょう。
また、この写真で標本にされているテンビンは外傷はなく附節も全て残っていましたが、元々やや羽パカ気味でした。
※そのため羽を開いた標本にしました。
そして外傷はないものの附節がたくさん取れて死んだものは、しっかり寿命を全うしたと言えるのではないでしょうか。
昨年秋までしっかり長生きして死んだブッパがそうでした。
狭いケース内なので、転倒したりして外傷ができてしまうのもやむなし、とは思います。
とは言え、家庭で飼育されているカブトやクワガタを野生に戻すことは不可能だし、してはいけないことです。
つい最近和歌山でオオクワガタが急に見られるようになった、というニュースもありましたが、あの大きさからすると、誰かが放したのではと感じました。
狭いケースでかわいそうやなぁ、とも思うのですが、自然環境下では多くの国産クワガタが絶滅危惧種に指定されているのだから、人間のための快適な環境で人工的に増やし、保存してやることもまた必要なのだと思います。